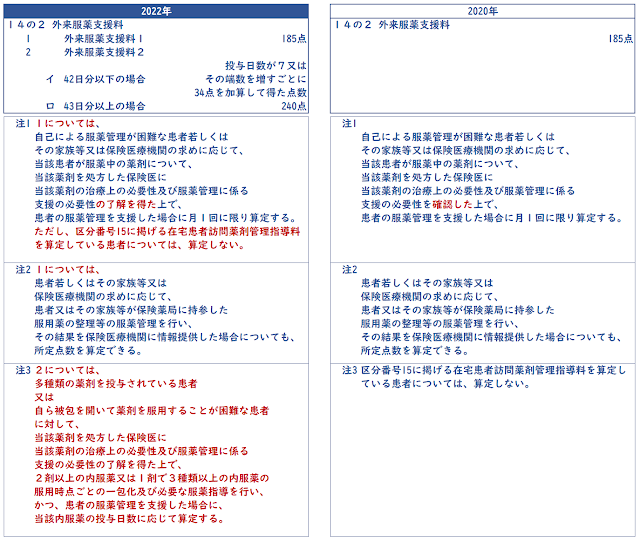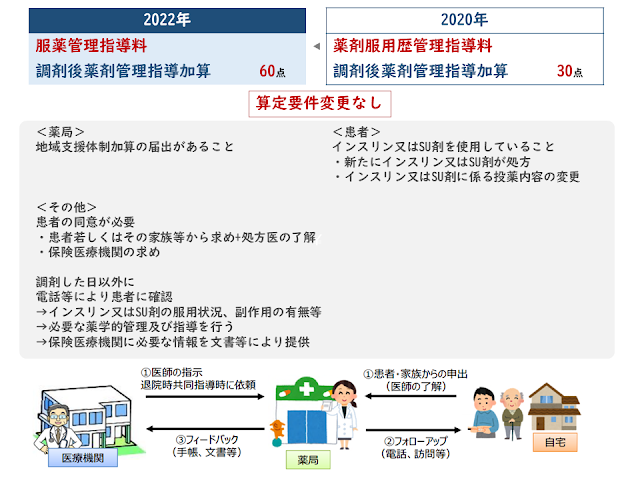2022年度の診療報酬改定では、オンライン資格確認システムを活用し、患者の薬剤情報や特定健診情報などを踏まえて調剤することへの評価として「電子的保健医療情報活用加算」(3点、月1回まで)が調剤管理料に新設されます。
オンライン資格確認システムを活用できる体制を有し、そのことを見やすい場所に掲示していることなどを算定要件として求められます。
なお、患者に関する薬剤情報などの取得が困難な場合については、2024年3月31日までは3カ月に1回に限り1点を加算する経過措置が設けられています。
施設基準の「電子資格確認に関する事項についての掲示」は、厚生労働省の「オンライン資格確認に関する周知素材について」を活用すると良いでしょう。
10の2 調剤管理料
注5(新) 電子的保健医療情報活用加算 3点(月1回)
[対象患者]
オンライン資格確認システムを活用する保険薬局において調剤が行われた患者
[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険薬局において、健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認により、患者に係る薬剤情報等を取得した上で調剤を行った場合は、電子的保健医療情報活用加算として、月1回に限り所定点数に加算する。
(※)健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認により、患者に係る薬剤情報等の取得が困難な場合等にあっては、令和6年3月31日までの間に限り、3月に1回に限り1点を所定点数に加算する。
[施設基準]
(1) 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和51年厚生省令第36号)第1条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。
(2) 健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。
(3) 電子資格確認に関する事項について、薬局の見やすい場所に掲示していること。
[健康保険法第3条第13項]
この法律において「電子資格確認」とは、保険医療機関等(第六十三条第三項各号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局をいう。以下同じ。)から療養を受けようとする者又は第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者から同項に規定する指定訪問看護を受けようとする者が、保険者に対し、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)に記録された利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法により、被保険者又は被扶養者の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。)の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、保険者から回答を受けて当該情報を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提供し、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から被保険者又は被扶養者であることの確認を受けることをいう。
[昭和五十一年厚生省令第三十六号]
<療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令>(療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求)
第一条 保険医療機関若しくは次に掲げる医療に関する給付(以下「公費負担医療」という。)を担当する病院若しくは診療所(以下単に「保険医療機関」という。)又は保険薬局若しくは公費負担医療を担当する薬局(以下単に「保険薬局」という。)は、療養の給付(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百四十五条に規定する特別療養費、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費及び高額療養費の支給を含む。第八号を除き、以下同じ。)又は公費負担医療に関し費用を請求しようとするときは、電子情報処理組織の使用による請求(厚生労働大臣が定める事項を電子情報処理組織(審査支払機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、療養の給付及び公費負担医療に関する費用(以下「療養の給付費等」という。)の請求をしようとする保険医療機関又は保険薬局の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して、厚生労働大臣の定める方式に従つて電子計算機から入力して審査支払機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録して行う療養の給付費等の請求をいう。以下同じ。)又は光ディスク等を用いた請求(厚生労働大臣が定める事項を電子計算機を使用して厚生労働大臣の定める方式に従つて記録した厚生労働大臣の定める規格に適合するフレキシブルディスク又は光ディスク(以下「光ディスク等」という。)を提出することにより行う療養の給付費等の請求をいう。以下同じ。)により行うものとする。